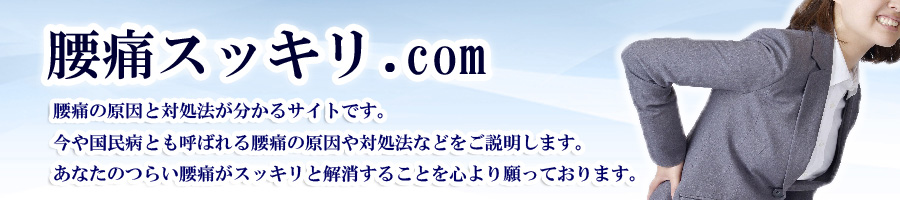腰椎分離症の禁忌、もしかするとやってるかも?

腰椎分離症の禁忌とは、どんなことでしょうか?
「腰椎分離症を指摘されたけど、痛くないから禁忌(やってはいけないこと)はない」と自己判断される方がいらっしゃいます。
もちろん、何をしても良いはずはありませんし、禁忌は存在します。
腰椎分離症は、腰の骨の一部が繰り返しのストレスによって疲労骨折のようになり、骨が離れてしまうものです。
疲労骨折のようと言っても、実は腰椎分離症はあまり強い痛みを出さない場合が多いですし、痛みがあっても一時的で気づかないことも多いです。
そのため、軽い腰痛だろうと病院を受診しない方、腰椎分離症を指摘されても痛みがないため、禁忌はないと思う方が多いようです。
ここでは、腰椎分離症の禁忌についてご説明します。
腰椎分離症の禁忌はたくさんある?
腰椎分離症の禁忌には、どのようなことがあるのでしょうか?
まず、腰椎分離症のやっかいな部分は、痛みが軽かったり、全くなかったりすることです。
腰椎分離症は、治るタイミングを逃すと基本的には治らないものです。
骨が離れたまま、成長していったり、年齢を重ねたりすることになります。
常に腰が痛くなるリスクや、分離した骨が前にずれるリスクを背負っていますから、禁忌もたくさん存在するのです。
さらに、治療を受ける場合も、禁忌をおかすケースは結構あります。
腰痛が出ても軽いものが多いので、腰椎分離症だと気づかないまま自己判断の治療をおこなったり、整骨院などで治療を受けたりすることがあります。
たとえば、腰椎分離症の「禁忌」として骨をバキバキ鳴らすことがあります。
これは、分離した部分がさらにズレてしまいます。
自分で鳴らすことが習慣という方も多いですし、整骨院などで骨のずれを治すといってバキバキ鳴らす治療をすることも多いようです。
その他でいえば、腰を引っ張る治療も「禁忌」となります。
すでに分離して何年もたっている腰椎分離症や、足のしびれがあるような場合は引っ張ることもあります。
しかし、基本的には分離した部分をさらに分離させる可能性があるため禁忌となります。
また、腰を反る動作、捻じる動作は禁忌ですので、生活習慣では特に注意が必要です。
整骨院などで、腰の治療と言って腰を反った状態をしばらく取らせる治療法があります。
もちろん腰椎椎間板ヘルニアなどほかの腰痛ではとても効果のあることがわかっているのですが、腰椎分離症に関しては禁忌となります。
まずは、腰の調子がおかしければ、一度はレントゲン等でチェックして見ましょう。
腰椎分離症の禁忌に対して注意する点は?
腰椎分離症の禁忌に対して注意する点は、どんなことがあるのでしょうか?
原則として、腰椎分離症は外見上から判断することは難しく、医療機関でレントゲンやMRIを撮ることでしか確認できません。
ありがたい、でも厄介なことに痛みそのものがそこまで強くないケースが多いです。
なので、医療機関を受診せずにほったらかしにしてしまうこともよくあります。
そうなると分離しているかどうかの判断ができません。
そのため、腰が痛い時はまず医療機関でチェックすることをお勧めします。
さて、禁忌に対する注意点ですが、腰を反ったり捻じったりの動作を繰り返さない、気持ちがいいからと言って腰の骨をバキバキと鳴らさないなどがあります。
生活習慣で禁忌をおかさないようにするために手っ取り早いのが、サポーターを使うことです。
重い荷物を抱えないといけなかったり、ずっと立ちっ放しなどの時だけ使うようにするとよいでしょう。
もちろん、サポーターは万能ではないので、普段からお腹に力をいれて動くのを意識することも、禁忌をおかさないためには大切です。
腰の骨をバキバキと鳴らすのは禁忌中の禁忌です。
よほど熟練の治療家なら、腰椎分離症の分離している部分以外だけを鳴らして矯正することができるでしょう。
しかし、素人の方が体をねじって自分で無理やり鳴らすのはあまりにも危険な禁忌です。
癖として、鳴らないとすっきりしないという習慣がついてしまうので、ついつい無意識に鳴らすということになります。
この禁忌は、腰椎分離症で分離している部分を痛めたり、より骨が離れてしまったりする危険性があるだけではありません。
離れかけている骨にとどめを刺してしまうことも考えられるのです。
腰椎分離症は、禁忌を知って適切な生活習慣をつければ、痛みなく生活していくことができます。
ご紹介した生活習慣は、そのほかの腰痛も防ぐことができるものですので、ぜひ参考にしてみてください。